小生が『源氏物語』を通読したのは、比較的最近のことである。二度ほど挫折を経験し、「三度目の正直」で読了することができた。
30歳の頃、友人たちと『源氏物語』の学習会をしてゐた。月に一度一巻づつ交替で担当者がレジュメを作つて講義をし、他のメンバーは該当巻を通読しておき、質問をしたり意見交換をしたりした。テキストは、当時評判の好かつた新潮社の「古典集成」(石田譲二・清水好子 校注)を用ゐた。並行して、勤務校の紀要に載せる論文(400字詰原稿用紙100枚くらゐ)のために『源氏物語』に関する論文を100以上読んだ。こんなに論文をまとめて読んだのは、大学の卒業論文を書いた時以来だつた。
しかし、「若菜」巻を過ぎた頃、何人かのメンバーに揃つて子どもが生まれて、なかなか集まることが難しくなり、学習会は立ち消えになつてしまつた。その後、小生は、独自に続きを読み進めたが、第三部のいはゆる匂宮三帖のあたりで挫折してしまつた。さらに40歳の頃にもう一度通読を試みたが、仕事が忙しくなつたこともあり、やはり同じ所で頓挫してしまつた。
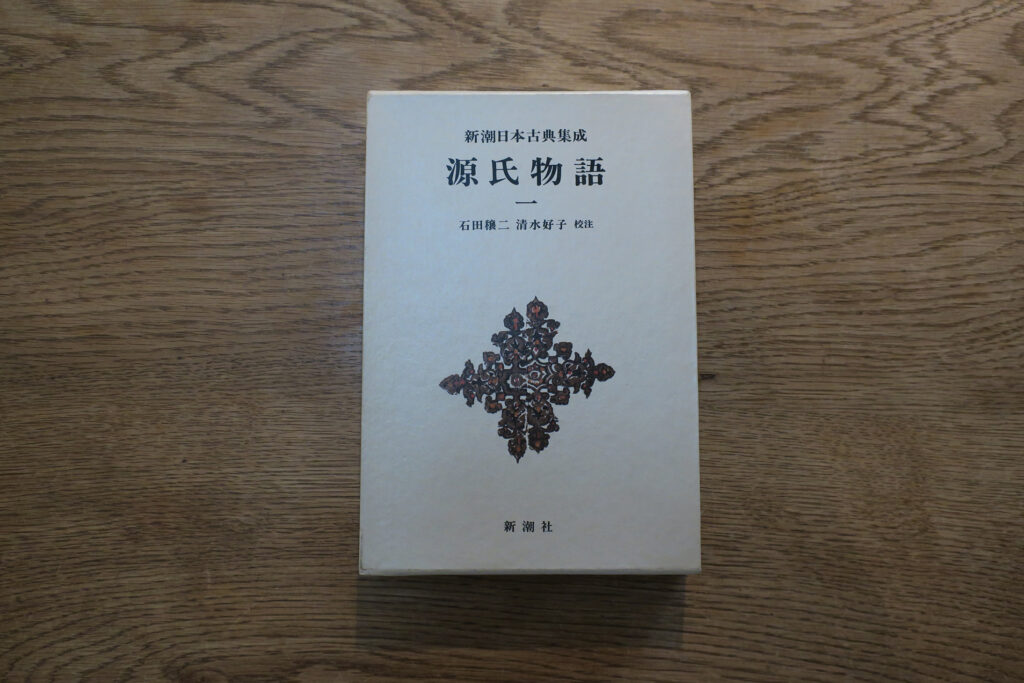
三度目に、岩波文庫の新版『源氏物語』(柳井滋・室伏信助・大朝雄二・鈴木日出男・藤井貞和・今西祐一郎 校注)で通読した。「新大系」を基にしてゐるが、補注など一部の注を省略する一方で、最新の研究成果を反映して注を改めた所もあり、今『源氏物語』を原文で読むには、これに拠るのがよいと思ふ。形式は、右ページが本文、左ページが注(部分訳)になつてゐて、基本的には見開きで完結してゐるので、読みやすいと思ふ。何より常時携帯できるのが好い。(各冊500〜700ページと、文庫本としてはかなり厚いけれど…。)

文庫版の『源氏物語』の注釈書には、他に角川文庫(ソフィア文庫)の『源氏物語』(玉上琢彌 訳注)がある。これは、角川書店の『源氏物語評釈』(玉上琢彌 訳注)を基にしたもので、注や解説の一部を省略してゐるが、全文の現代語訳が付されてゐる。脚注形式で、後ろに補注と現代語訳が付されてゐる。文庫版で全文の現代語訳が必要な場合には、こちらを用ゐるしかない。
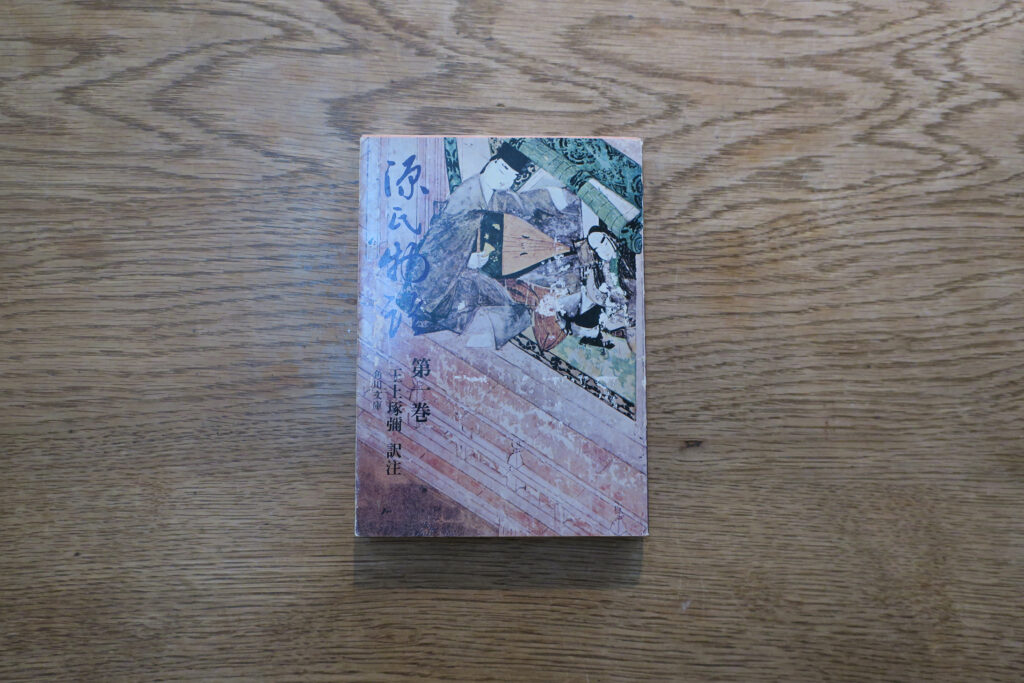
教材研究をする際には、小生の場合、昔は新潮「集成」と小学館「全集」(阿部秋生・秋山虔・今井源衛 校注・訳)と角川「評釈」を用ゐたが、近年は小学館「新編全集」(阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男 校注・訳)と岩波「新大系」(柳井滋・室伏信助・大朝雄二・鈴木日出男・藤井貞和・今西祐一郎 校注)を基本にし、必要に応じて角川「評釈」と新潮「集成」を参照してゐた。注は、「評釈」が最も詳しく、次に「全集」が詳しいが、「新編全集」「新大系」はそれ以後の研究成果を踏まへてゐる。「集成」は注は簡素な代はりに本文の傍にセピア色で部分訳を付してゐる。
小生は、小学館から「完訳日本の古典」(阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男 校注・訳)が出始めた時に購入してしまつたので、さすがに「新編全集」を買ひ直す余裕は無く、自宅では「完訳日本の古典」を用ゐ、職場では「全集」「新編全集」を使用した。(「完訳日本の古典」は「全集」を基に注を簡素にしてゐるが、校注者に鈴木日出男が加はり、底本・注・訳を見直してゐる。)
現代語訳の無い注釈書では、注のある箇所しか解釈が示されてゐないので、全文の解釈を知りたい場合には、全文に現代語訳の付されてゐる注釈書を見る必要がある。(萩谷朴は、『枕草子解環』の凡例で、「解釈の最終的な結論を明示している」条件を「全文の口訳を備えているもの」としてゐる。)主な注釈書で全文に現代語訳がなされてゐるのは、角川「評釈」と小学館「新編全集」(現代語訳の担当は秋山虔)くらゐであり、「新編全集」の秋山のものが、注釈としての現代語訳として、現在では最も優れてゐると思ふ。ただ、最近、勉誠社から『正訳源氏物語 本文対照』(中野幸一 訳)が出た。これは、現代語訳と本文を上下段で対照させる形で、注釈書に準じたものになつてゐて、訳文も原文に忠実でありながら自然な日本語になつてゐる。(現代語訳については、また別に語らうと思ふ。)

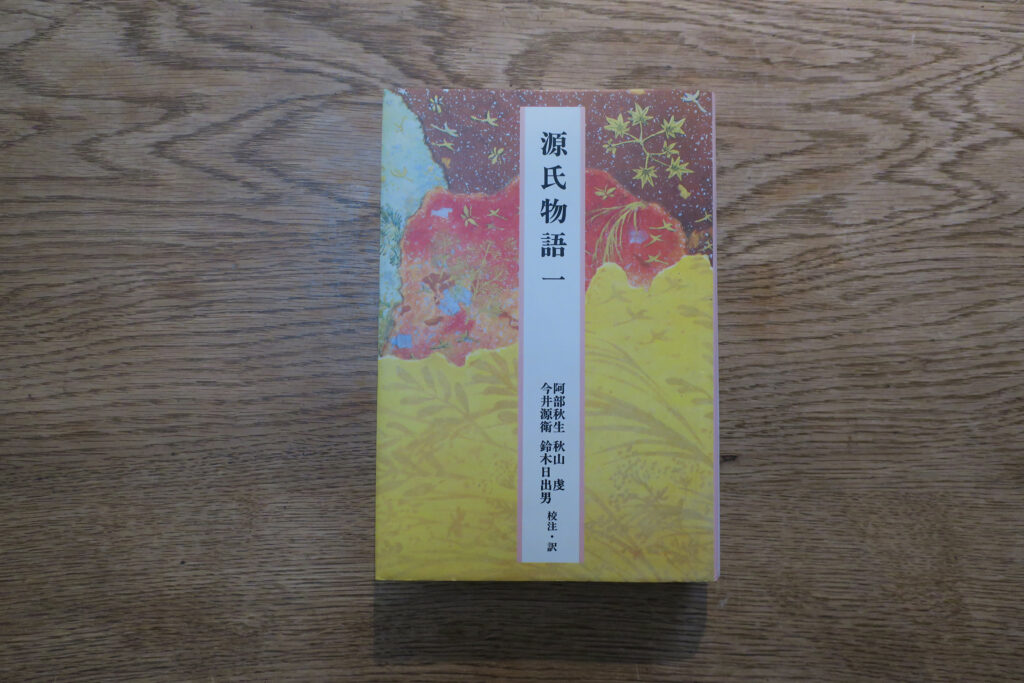
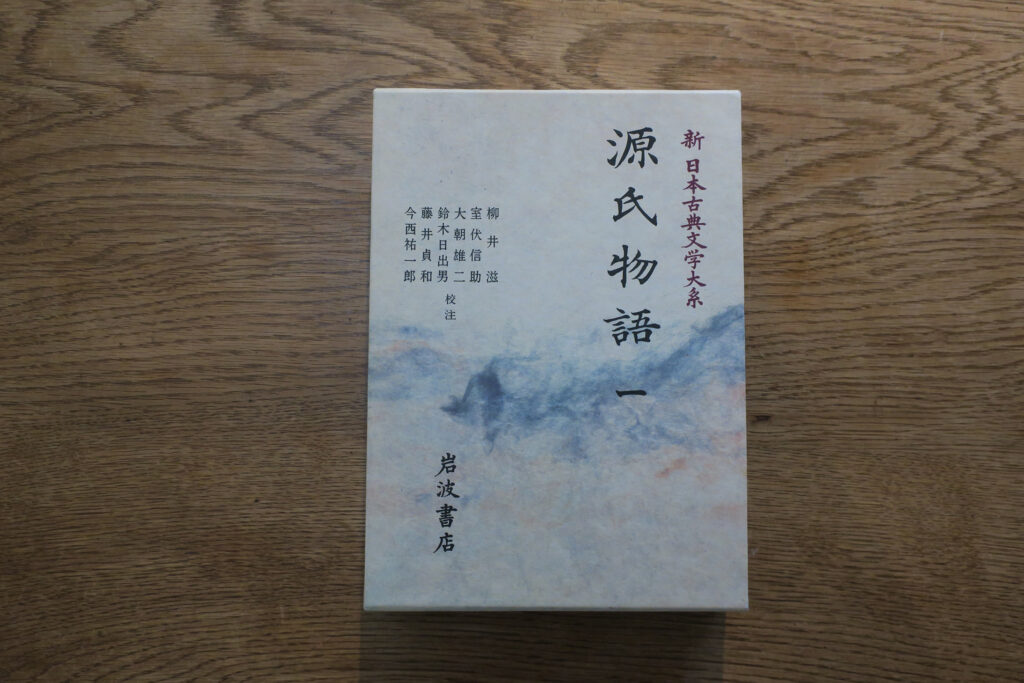
さらに最近、和泉書院から『源氏物語全解読』(小田勝 訳注)が出始めた。小田は、国語学者で、『読解のための古典文法教室 大学生・古典愛好家へ贈る』(和泉書院)など古典文法に関するさまざまな著作がある。この注釈書も、一文ごとに文法的に詳しい解説がなされてをり、教材研究のため文法的に精密に読まうとするには有益である。ただ、まだ(本稿執筆時)第一巻(桐壺から夕顔まで)しか刊行されてゐない。
趣味として読む場合はともかく、教材研究として読む場合には、教材として読む箇所全文を自分で現代語訳してみるべきである。何となく解つてゐるつもりでも、自分で訳さうとすると、理解の浅い箇所や解釈の曖昧な箇所に気付くことができる。ゼロから訳すのが大変なら、指導書の訳を基にして、原文と対比しながら各注釈書を踏まへた自分の理解に従つて修正していけばよい。
『源氏物語』の現代語訳について知りたい人は、『源氏物語』の現代語訳の案内をした以下の投稿を見られたし。
『源氏物語』の現代語訳案内の投稿へのリンク
https://seiyu-udoku.jp/『源氏物語』その二%E3%80%80現代語訳/




コメント
高校の国語科の教師です。古典の中でも「源氏物語」は難しく、私の周囲でも最後まで読み通した人はほとんどいません。職場には小学館の古い「古典文学全集」がありますが、皆さん教材研究で使うので、私が独占するわけにはいきません。自分で買い揃えるとなると、携帯することと部屋に置くスペースも考えて、文庫になりますね。紹介していただいた岩波か角川の文庫で、私もチャレンジしてみようと思います。
確かに『源氏物語』は、語彙も多く人間関係も複雑で、決して読みやすい作品ではありません。表現も重層的で、深い理解にはさまざまな引用を把握する必要もありますが、現代の我々には、平安末以来の研究の蓄積があります。こちらの読みが深まれば、必ずそれに応へてくれる偉大な作品です。ぜひ、チャレンジしてみてください。