2025.06.22
久保朝孝 編『王朝女流日記を学ぶ人のために』(世界思想社)読了。
蔵書を整理してゐると、読まうと思つて買つたまま読まずにゐた(積ん読)本としばしば再会する。主立つた作品について調べる際に参考にしようと、世界思想社の『○○を学ぶ人のために』シリーズを何冊か買つた中の1冊であるこの書を見付けた。(昔は、學燈社の雑誌『國文學 解釈と教材の研究』の別冊『○○必携』シリーズを買ひ揃へてゐた。至文堂の『国文学 解釈と鑑賞』といふ雑誌もあつたが、今はどちらも廃刊。東京大学国語国文学会編の『國語と國文學』は出版社をいくつか変へながらからうじて存続してゐるが、これはより学術誌的色彩が強い。)
『王朝女流日記を学ぶ人のために』は、愛知淑徳大学のエクステンションセンターが開設したウィークエンドカレッジの講座「王朝女流日記の世界」を基盤としてゐるさうだ。連続10回の講座で、10人の講師は、編者いはく「女流日記を含みながらも、どちらかと言えば物語文学や和歌文学などを専門領域としてすぐれた研究を積み重ねている方々」であり、「『女流日記』とは何かという問題をあらためて根本から問い直すために、そしてそれぞれの作品から未発の新しい価値をすくい出すことをめざして、あえてそのような布陣にした」さうだ。
長く積ん読になつてゐたが、「古典への扉」の投稿でこのところ日記文学を取り上げてゐることもあり、通読した。20年近く前に出た本なので、現在の研究はさらに進んでゐるのだらうが、専門外の小生には、学び直しになり役立つたところもある。
第一章「王朝女流日記への招待」(三角洋一)と第十章「王朝女流日記の達成」(中野幸一)は総論で、第二章から第九章までで、「土佐日記——〈性差〉と〈言説〉と」(長谷川政春)・「歌人道綱母——蜻蛉日記上巻の本質」(後藤祥子)・「枕草子——つれづれなぐさむ草子と日記」(高橋亨)・「和泉式部日記の成立——もの思ふ女の記」(平田喜信)・「紫式部日記の消息体文——その不思議な表現世界」(室伏信助)・「更級日記の始発——少女のまなざしをめぐって」(原岡文子)・「成尋阿闍梨母集——母から子へのメッセージ」(伊井春樹)・「讃岐典侍日記の叙述方法——排除・密着=独占の構図」(久保朝孝)と8つの作品について、各講師が自分の設定したテーマで語つてゐる。
『蜻蛉日記』の「百人一首」にも採られて有名な「嘆きつつ…」の和歌が読まれた経緯についての文章を取り上げてみる。(後藤の論は多岐に渡るが、ここでは『蜻蛉日記』と『大鏡』との違ひについて、後藤と中野の文章を参考にしながら、小生の視点で取り上げる。)この段は、高校の古典の教科書にもよく採られてゐるので、多くの人が読んだことがあると思ふ。(引用は本書に拠る。引用の後に、小生の要約を付す。)
さて、九月ばかりになりて出でにたるほどに、箱のあるを手まさぐりにあけて見れば、人のもとにやらむとしける文あり。あさましさに、見てけりとだに知られむと思ひて書きつく。
疑はしほかに渡せるふみ見ればここや途絶えにならむとすらむ
など思ふほどに、むべなう、十月つごもりがたに、三夜しきりて見えぬ時あり。つれなうて、「しばしこころみるほどに」、などけしきあり。
夫が忘れていつた文箱を何気なく開けてみると、他の女宛ての手紙があつた。呆れた作者は、自分が見たといふことだけでも伝へようと、その手紙の端に「他の女に渡す手紙があるのを見ると私の所はお見限りなのでせうか」といつた歌を書き付ける。夫は、十月末に三夜続けて訪れないことがあつた。(他の女と結婚したか。)
これより夕さりつ方、「内裏の方、のがるまじかりけり」とて出づるに、心えで人をつけて見すれば、「町の小路なるそこそこになんとまりたまひぬる」とて来たり。さればよといみじう心憂しと思へども言はむやうも知らであるほどに、二三日ばかりありて、暁方に門を叩く時あり。さなめりと思ふに憂くて開けさせねば、例の家とおぼしき所にものしたり。つとめて、なほもあらじと思ひて
嘆きつつひとり寝る夜の明る間はいかに久しきものとかは知る
と、例よりはひきつくろひて書きて、うつろひたる菊に挿したり。返りごと、「あくるまでもこころみむとしつれど、とみなる召使の来あひたればなむ。いとことわりなりつるは。
げにやげに冬の夜ならぬ真木の戸も遅くあくるはわびしかりけり」
さても、いとあやしかりつるほどに、事なしびたり。しばしは忍びたるさまに、「内裏に」など言ひつつぞあるべきを、いとどしう心づきなく思ふこと限りなきや。
夫は「宮中に行く」と言つて出ていつたが、不審に思ひ召使に後を付けさせると、「町の小路のどこそこに車をお停めになりました」と報告してきた。作者が辛いと思つてゐると、明け方に誰かが門を叩く。夫が来たのだらうと思ふが、辛くて開けさせずにゐると、夫は町の小路の女の家と思はれる所に行つてしまつた。朝になつて、作者は「あなたの訪れを待ちわびて悲しみ嘆きながら一人で寝る夜の明けるまでの間がどんなに長いものかお解りでせうか」といふ歌を、いつもよりも丁寧に書いて、色変はりした菊に挿して送つた。夫は、「戸が開くまで待たうと思つたのだが、急用を知らせる召使が来たので…。あなたがお怒りなのはもつともです。…」と返事を寄越す。
この場面の経緯や作者の気持について、注釈書によつて解釈が違ふのも興味深いが、ここでは『大鏡』との違ひを見てみよう。このくだりを『大鏡』では
殿のおはしましたりけるに、門をおそくあけゝれば、たびたび御消息いひ入れさせたまふに、女君、
嘆きつつひとり寝る夜の明る間はいかに久しきものとかは知る
いと興ありとおぼしめして
げにやげに冬の夜ならぬ真木の戸も遅くあくるはわびしかりけり
とあつさりと記してゐる。そして、ここでは兼家は立ち去らず、その場で和歌の応酬が行はれてをり、兼家は作者の和歌に感心し、作者の家に入つたと思はれる。
どちらが事実かは判らないが(一般には日記が事実を書いてゐると思ふだらうが、日記とて記憶違ひもあれば脚色もあり得る)、同じ場面がそれぞれの作品にふさはしい文脈で語られてゐる。『蜻蛉日記』がその序で「世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで世に経る人」の「人にもあらぬ身」の日記だと述べてゐるのに対し、『大鏡』は、『蜻蛉日記』について、「この母君(道綱の母)、極めたる和歌の上手にておはしければ、この殿(兼家)の通はせ給へりけるほどの事、歌などかきあつめて、かげろふの日記と名付けて世にひろめ給へり。」と記してゐる。『蜻蛉日記』は、晩年になつて自己の半生を回顧して、幸福とは言へなかつたはかない人生を描かうとしたもので、夫の冷淡に対する閨怨の情が基調にあるが、『大鏡』は、受領の娘が和歌の上手であつたがゆゑに権門の妻になつた幸ひを日記に書いて広めることができたといふ認識である。『大鏡』はおそらく男性貴族である作者が(『栄花物語』などに比べれば批判精神はあるものの)藤原氏の繁栄を描く歴史物語であり、「嘆きつつ…」の段もさうした歴史の中の(男性貴族の視点からの)和歌説話的な挿話になつてゐる。
『蜻蛉日記』に限らず、どの日記も、作者のかけがへのない人生が、独特の語り口で切実に語られてゐる。ぜひ、手に取つて〝彼女の人生〟に触れてみてほしい。

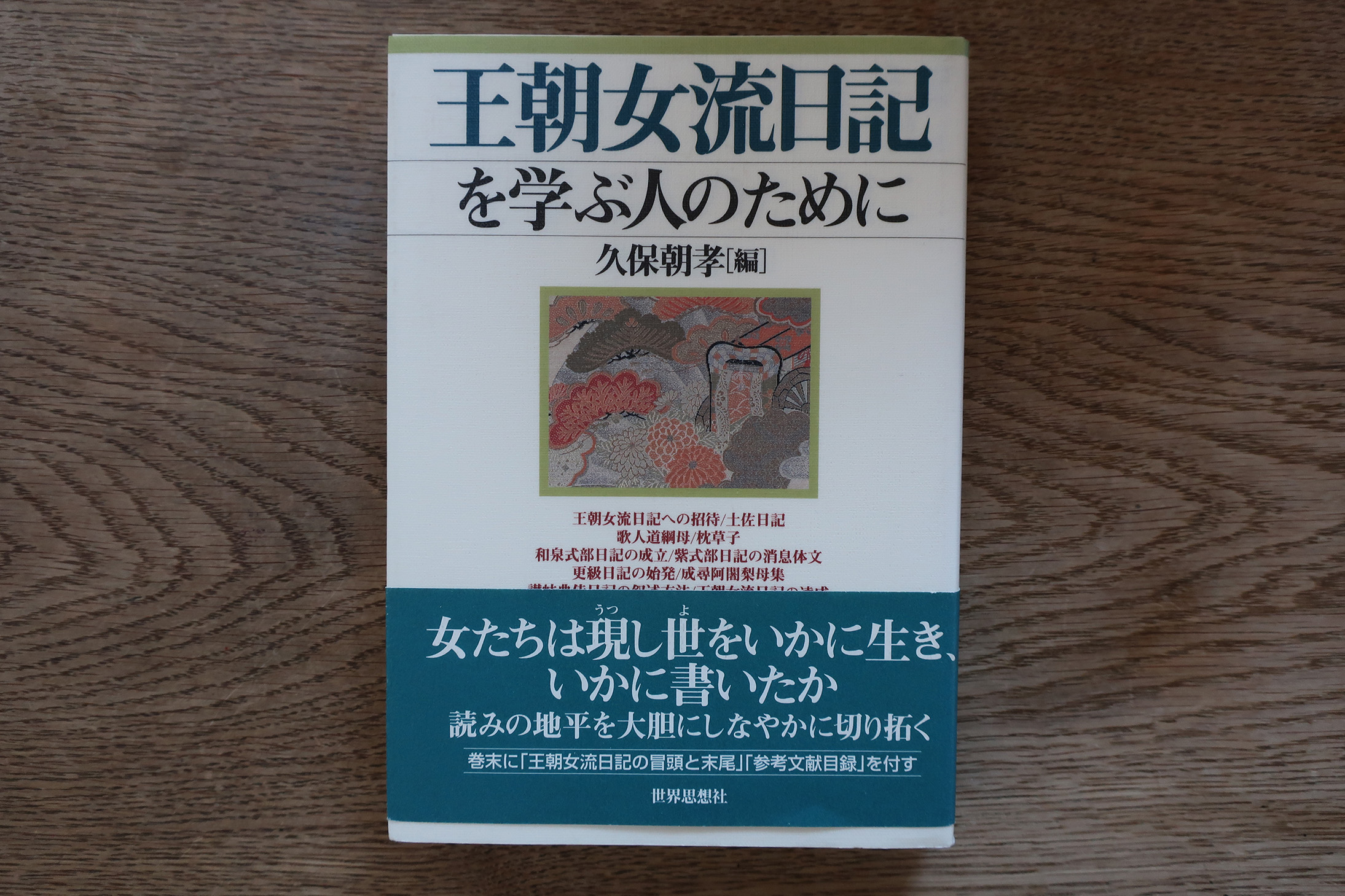


コメント