2025.10.02
今では、阿波踊りやねじめ正一の直木賞受賞作『高円寺純情商店街』でも有名だが、東京のローカルな高円寺の名を全国区にしたのは、吉田拓郎である。拓郎(この当時は「よしだたくろう」名義)のアルバム『元気です。』(1972)に収録された「高円寺」といふ曲で日本中の多くの若者が「高円寺」といふ地名を知つた。曲は、E7とA7の2つのコードだけで(拓郎自身の解説に拠る)、歯切れの好いストロークが繰り返される。歌詞は、日常のとりとめのない心情が語られるだけだが、詩も曲も新鮮だつた。下に歌詞を掲げておく。(赤字は、小生に拠るもの。)
君を好きだなんて言ったりすると 笑われそうな気がして
とても口に出すのがこわかったけれど
気がついてみたら 君の方が僕を好きになっていて
それで口に出さないでも よくなったんだよ君は何処に住んでいたのですか 高円寺じゃないよね
だって毎日電車に乗っても 違う女の子に目移りばかり
それで電車に乗るたびに いつも色んな女の子に
ふられていたんだものね君の事好きだなんて言わないでよかったよ
電車は今日も走ってるものね
今日は、高円寺界隈(南側)を散歩する。

JR中央線「高円寺駅」の南口を出て、ロータリーを過ぎ、左斜め(東南)の坂道を進むと、「氷川神社」がある。祭神は、素戔嗚尊(すさのをのみこと)。
境内に日本で唯一の「気象神社」があるといふことで、門前にはその日の気象情報が掲示されてゐる。


境内に「気象神社」がある。祭神は八意思兼命(やごころおもひかねのみこと)。下駄の形の絵馬がユニークである。気象予報士の合格祈願やイベントの日の晴天祈願などに訪れる人が多いさうだ。

「氷川神社」の前の坂道をさらに下ると「高円寺中央公園」がある。近くの保育園の子どもが保育士に連れられて来てゐた。

「高円寺中央公園」に接する道を南に進むと、ライブハウス「高円寺HIGH」がある。(午前中なので店は当然閉まつてゐるが…。)隣の阿佐ヶ谷はジャズの街だが、高円寺はフォーク&ロックの聖地で、多くのライブハウスがある。

「高円寺HIGH」から東に進むと、「高円寺」の地名の由来となつた曹洞宗の「宿鳳山 高圓寺」がある。「中央線あるあるPREOJECT なみじゃない、杉並!」(中央線あるあるプロジェクト実行委員会)に拠れば、「江戸時代、この辺りは将軍家の鷹狩りの狩場の1つで、三代将軍徳川家光が遊猟のおり寺に立ち寄り、『小沢村』だった村名を『高円寺村』と改めさせた」といふ。
「高圓寺」に限らず、この辺の寺は、門の前に柵が置かれ、檀家以外の参拝を拒絶してゐるところが少なくない。防犯のためのやうだ。

「高圓寺」の西側の道を南に進むと、途中で「桃園川緑道」と交叉する。
「桃園川緑道」は、「荻窪駅」近くの「天沼弁天社」内の湧水で生じた弁天池を水源とする「桃園川」を暗渠化し、その上に整備された緑道。「阿佐ケ谷駅」と「高円寺駅」の間にある「杉並区立けやき公園」の南から始まり、杉並区・中野区を横断し、中野区と新宿区の境界を流れる神田川まで(道路や建物で途切れながら)続く。(2024年10月21日の「阿佐ヶ谷南」の投稿でも紹介してゐる。)

住宅街を抜けると「ふらっとすぎはち」がある。「ふらっとすぎはち」は、「旧杉並第八小学校」の跡地を活用した地域コミュニティ施設で、「高円寺図書館」「コミュニティふらっと高円寺南」「すぎはち公園」「高円寺東保育園」の複合施設である。


「ふらっとすぎはち」の近くには、多くの寺院がある。下の写真は、順に「福壽院」「宗泰院」「松應寺」「長龍寺」(すべて曹洞宗)。すべての寺院は廻れなかつた。




さらに南に進むと、青梅街道にぶつかる。(下の写真は、青梅街道が環七と交叉する所にある梅里歩道橋から眺めた青梅街道。)

(上の写真の左端に見える)「華屋与兵衛」の西側の道を南に進むと、左手に「セシオン杉並」(杉並区立公民館を引き継いだ社会教育センターと地域区民センターの複合施設)があり、さらに進むと右手に「堀ノ内斎場」がある。


さらに進むと、「妙祝寺」「修行寺」(いづれも日蓮宗)などの寺院がある。


さらに南には、「妙法寺」(日蓮宗)がある。寺の由来は、「妙法寺」のHPによれば、「今を去る事四百年以上前、元和(1615~1623)の頃、元真言宗の尼寺であったが、覚仙院日逕上人は老母妙仙院日圓法尼の菩提のため、日蓮宗に改宗し、老母を開山とし、日逕上人自らは開基第二祖となられた。山号は開山日圓上人にちなみ日圓山とし、寺号を妙法寺と号した。」さうだ。祖師堂に安置する日蓮大聖人像は、「除厄け祖師」と呼ばれ、広く信仰を集めてゐるとのこと。


吉田拓郎のアルバム『人間なんて』(1971)のジャケット写真は、当時拓郎が住んでゐた高円寺のマンション(現在の感覚ではアパート?)の外階段で撮影したものである。(実際にはマンションは地下鉄丸ノ内線の「新高円寺駅」よりも南の堀ノ内にあり、「高円寺駅」からはかなり遠いけれど…。)「妙法寺」の近くのその場所を訪ねてみると、面影を残す建物があつた。(50年も前の建物なので、当時のままではなく改修等はなされてゐると思ふ。「引っ越しの詩 拓郎東京物語」といふ拓郎が住んでゐた家を巡るTVの特別番組で見た時と比べて、外壁の塗装は綺麗になつてゐた。)マンションとはいへ個人の住居なので写真を載せるのは控へるけれど…。

午餐の時間が近付いたので、「高円寺駅」の方に戻る。
青梅街道を西に進み、五日市街道(青梅街道より北は高南通り)と交叉する「五日市街道入口」交叉点を渡ると、丸ノ内線「新高円寺駅」がある。南側の出入口の脇には「AYUMI BOOKS」がある。書店の閉店が相次ぐ昨今、頑張つてほしいものだ。


「新高円寺駅」の北側の出入口の先、「みずほ銀行」の手前から「高円寺ルック商店街」が始まる。(「高円寺駅」から来るとここが南端。)「高円寺パル商店街」を経て「高円寺駅」まで繋がる南北に長い商店街である。ファッション(古着店も多い)・輸入雑貨や飲食などさまざまなジャンルの店舗が連なり、歩いてゐるだけでも愉しい。





インド・ネパール・アジア諸国直輸入衣料雑貨の「仲屋むげん堂」は知つてゐる人も多いだらう。

小生は、「珈琲亭七つ森」で午餉。「野菜カレー」と「チャイ」を注文する。カレーは、南瓜・パプリカ・大根など種々の野菜が入つてゐてスパイスも効いてゐた。


商店街には、昭和6年創業の古書店「大石書店」もある。頑張つてほしい。

「ルック商店街」から脇道に入つた所の古いビルの2階に「蟹ブックス」といふ小さいけれど個性的な書店もある。(今日は定休日だつた。)適宜ブックフェアや展示なども実施してゐる。

「ルック商店街」も「桃園川緑道」と交叉する。下の写真は西側で、この道が「阿佐ヶ谷駅」の近くまで続いてゐる。

「桃園川緑道」より北は「高円寺パル商店街」で、アーケードになつてゐる。100円ショップやドラッグストアのチェーン店などもあるが、古着屋も多い。(以前から高円寺は下北沢と並んで古着屋が多かつたが、最近さらに増えたんぢやないかな。)



「パル商店街」の途中、「日王山 阿遮院 長仙寺」の山門に向かふ路地には、飲食店が軒を連ねてゐる。

「長仙寺」は、真言宗豊山派の寺院。本堂は、戦災のため全焼したので、現在の本堂は、1969年に建立されたもの。

路地の古いビルの2階に「読書喫茶室 アール座読書館」がある。入口は、ちと判りづらい。階段を昇ると、左手に入口があるが、マンションのドアそのままである。ドアの横に注意書きが貼つてある。


「アール座読書館」のHPにある「アール座読書館 ご利用法」を引く。
アール座読書館は読書喫茶室です。
都会の中に、木々に囲まれてお茶を飲みながら本が読める静かな空間があってもいいなと思ったのが、開店のきっかけです。
なので大変恐縮なのですが、長いお話、声高なお話し声はご遠慮いただいておりますので、お話目的の方はご遠慮下さい。
無収入の身の小生にとつてカフェに通ふのは贅沢なのだが、それでも時には街歩きに疲れて休息したりボーッとした時間を過ごしたり読書をしたりするために、カフェに憩ふこともある。ところが〝喋るのをやめたら死んでしまふ〟と思つてゐるんぢやないかと思はれる人たちのグループが入つて来て小生の近くの席を陣取つて一瞬も途切れること無く話し続けて、辟易することがある。
この店は、私語をする者はをらず、聞こえてくるのは扇風機の羽根の廻る音くらゐなので(エアコンは窓に付けるタイプのものがあつたがこの日は稼働してゐなかつた)、読書に集中することができる。小生は、カプチーノを注文し、90分ほど読書に専念した。(アンティーク調の店内は懐かしい感じで、植物も置かれてゐてホッとするが、正直に言ふと椅子は座り心地が好いとは言へない。)数人ゐた客は皆自分の本を読んでゐたが、店の奥の壁一面に書棚があり、そこの本を借りて読むこともできる。

下は、駅側からの「パル商店街」入口の写真である。

「パル商店街」を歩き高円寺駅前まで来ると、高架下の商業施設「高円寺マシタ」がある。「JR東日本都市開発」の「高円寺マシタ」HPには、「『高円寺らしさを高円寺の皆さまとともに一緒につくっていきたい』/その想いを実現できるように『パブリックスペース』や『広場』を設け 高円寺の盛り上げを皆さまと創り出していきます」と書かれてゐる。
いくつかの店舗があるが、角にある「パンとビストロ 高円寺FLAT」はいつも賑はつてゐる。その向かひには、黄色い看板が目立つ「いりこ出汁 讃岐うどん いぶきうどん」がある。


今度は、駅の北側も歩いてみよう。



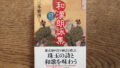
コメント