2025.01.10
森鷗外『歴史其儘と歴史離れ 森鷗外全集14』(ちくま文庫)読了。
ちくま文庫版『森鷗外全集』は、筑摩全集類聚版『森鷗外全集』を元に文庫化したもの。ただし一部は底本として岩波書店版『鷗外全集』を使用。全集といつても、岩波版ほど網羅的ではなく、医学論文等は除く。文学的文章は大半を収録するが、翻訳などは収録してゐないものもある。
『歴史其儘と歴史離れ 森鷗外全集14』は、その最終巻で、有名な「没理想論争」などの評論・随筆や詩歌を収録する。最終巻だが、小生、全巻読破したわけではない。日記の巻は未読だし、小説や翻訳も未読のものが何巻かある。
坪内逍遙との「没理想論争」は、明治維新以後まだヨーロッパの近代文学が輸入されて日が浅く、日本の近代文学は成熟してをらず、現代から見れば論争自体は単純だが、文学理論の用語も定着してゐないため、馴染みの無い哲学用語や仏教用語を借用したり、生硬な文章になつてゐる。しかも、鷗外の文章は、韜晦もあり回りくどく、解りにくい。ただ、かうした鷗外や逍遙の熱意や努力が、その後の日本近代文学の普及・発展の礎となるのである。
「仮名遣意見」は、「第三回 臨時仮名遣調査委員会」の席上の発言で、文部省の発音を写す改訂案を廃案に追ひ込んだものである。勿論意見の異なる部分もあるが、仮名遣ひに関する基本的な考へ方は、小生と近い。少し引用してみる。
一体仮名遣を観るにはおよそ三つの方面から観察することが出来ようと思います。即ち一は歴史的の方面である。一は発音的即ちPhonetikの方面である。その外にまだ語原的即ちEtymologieから観ると云う見方がございますけれども、これは先ず歴史的とある関係を有って居るように思います。一国の言葉が初め口語であったのが、文語になる時に、この日本の仮名のように音字を用いて書上げると云う、そう云う初めの場合には、無論仮名遣は発音的であるには違いない。然るにその口語と云うものは段々変遷して来る。一旦書いたものがその変遷に遅れると歴史的になる。そこで歴史的と云うことが起って来ます。それであるからどの国の仮名遣でも保守的の性質と云うものを有っているのは無論である。…仮に今日発音的に新しくある仮名を定められたと考えましょう。そうしたならばこの新しい仮名遣がまた間もなく歴史的になってっしまうのであります。語原的と申す意味を此処に説明しますると云うと、これは歴史的と密接の関係を有って居ります。外の国のOrthographieにおいて語原的と云うことには一種の特殊な意味を有たせてあります。一例を以て言いますると、国語の「すう」ということはこれを「すゑ」と云うときには和行の「ゑ」を書く。これは独逸の例で言いますと、独逸で「愛する」と言う詞でliebenと云う動詞があります。これを形容詞にするとliebとなります。けれども「プ」の字を書かずに「ブ」の字を書いてある。こう云う意味に仮名遣の発音と相違する点を、主もに語原的と外国では申して居るようであります。
(上記引用文の注)
「すう」…据う。ワ行に活用する。
「すゑ」…「据う」はワ行に活用するので、「ゑ」字をあてる。「すえ」と書くと、ヤ行動詞「すゆ」(饐ゆ、食物が腐敗して酸くなるの意)の活用形となる。
「lieben」は「リーベン」と発音し、「lieb」は「リープ」と発音する。
私も仮名遣に正と邪があるとは云いませぬ。しかし前にも申します通り口語こそ変遷を致しますけれども、文語に変遷ということはないのであります。衰替現象で変わってくるのでありますからして、口語の変遷を何時も見て居て、その中固った所を拾い上げては仮名遣を訂して行くと云う様なことならば、漸を以てしても宜しかろうと思いますけれども、その文語に定って居るものは正として、これを法則として立って置いて宜しいかと思うのであります。
第一に仮名遣は成程性質上から保守的なものである。しかしながら発音的の側から見ても大なる不都合があるものとは認めない。それ故に教科書などではやはり仮名遣の正則としてこれらを用いられたい…。第二は仮名遣は発音的に改めると云うことを為し得るものである。政府は極く慎重に調査して漸を以て改められるが宜しい。その時には国語を浄めると云うことを顧慮して、徐々に直されたい。…
要するに、「仮名遣ひは、語源や内在する論理を尊重するべきで、誤用や発音の変化を受け入れて改訂するには、それが定着した場合に、慎重に徐々に行はれるべきである。発音に合はせる形で仮名遣ひを定めると、発音はすぐに変化してしまふので、またすぐに決め直さなければならなくなる。(地域による違ひもある。)外国語でも、発音と綴り字(スペル)にズレがある場合は少なくない。」といつた良識的な意見である。
小生(福田恆存や石川淳や丸谷才一や塚本邦雄や白川静も)に言はせれば、現代仮名遣ひや常用漢字体は、日本語や漢字に内在する本来の論理を破壊した醜悪なものである。
「うた日記」は、鷗外が日露戦争に従軍した際に書いた詩歌集である。
海の氷こごる 北国も
春風いまぞ 吹きわたる
三百年来 跋扈せし
ろしやを討たん 時は来ぬ(「第二軍」第一連)
といつた、ロシアを討たうといふ出征前の勇ましい気持を歌つたものもあるが、
屍より 叢雲涌きぬ
ひたと来て 身にまつはるや
縫目なき ひとへ黒衣
そは蠅なりき(「かりやのなごり」第四連)
と、死体から涌き出た黒い雲のやうな蠅が自分に纏はりついたといつた戦場のグロテスクな悲惨を歌つたもの、病気の娘を思ふ歌、出征兵士の妻の心情を歌つたものなど、その内容は多岐に渡る。日露戦争の実態を知るといつた歴史的な意味でも重要な詩歌集である。
鷗外全集の未読の巻を読まねばとも思ふのだが、他にも読むべき本が多いのが悩みの種である。

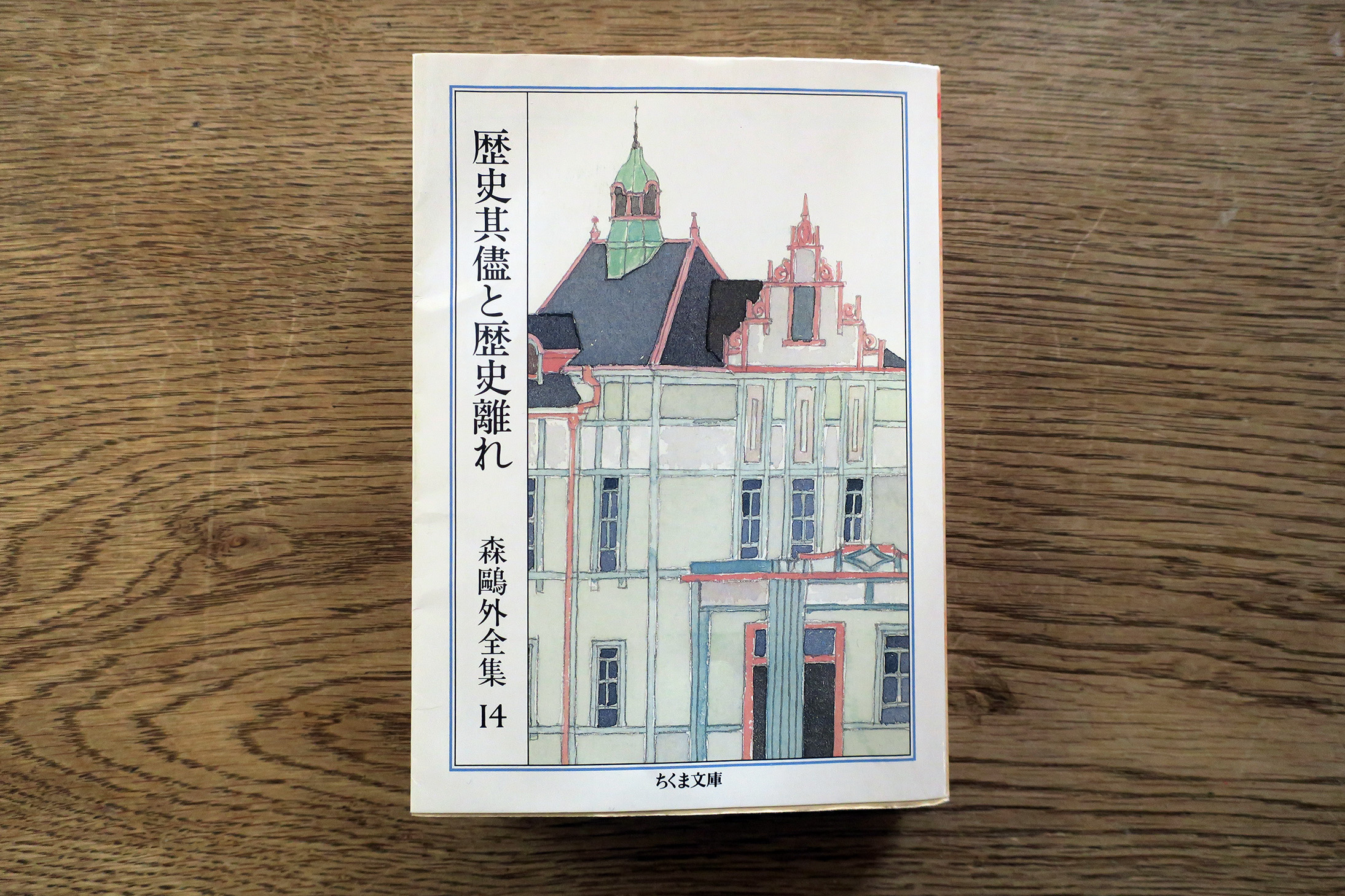


コメント