2025.07.30
宮崎市定『史記を語る』(岩波新書)読了。
小生、主要な古典に関しては、その作品の特質や歴史的な位置付けを把握するために、入門書や概説書を何冊か、作品によつては専門書も何冊か、読むやうにしてゐる。きちんとした著述だと、巻末に参考文献が載つてゐるので、さらに読書を拡げたり深めたりすることができる。
『史記』に関しては、学生時代に武田泰淳『司馬遷—史記の世界』(講談社文庫)・吉川幸次郎『漢の武帝』(岩波新書)、その後貝塚茂樹『史記 中国古代の人々』(中公新書)・加地伸行『「史記」再説』(中公文庫)などを読んだ。
この『史記を語る』も読まうと思つて買つてそのままになつてゐたのを、蔵書の整理をしてゐて見付け、恥づかしながらやうやく読み通した。懐かしい「黄版」(1992年発行の第4刷)である。現在は、「岩波文庫」の青帯で刊行されてゐる。(「『史記』の中の女性」を併収。)
著者の宮崎市定は、中国史研究の泰斗である。最初の2章「史記読法——史記はどう読まれてきたか——」・「正史の祖——紀伝体の創始——」で総論的に〝『史記』の受容〟・〝『史記』の体裁(方法)〟について述べ、その後「本紀」「世家」「表」「列伝」の順に解説してゐる。既発表の論文はなるべく使はずに、別の観点から稿を起こしたものである。学術論文ではないので、筆者自身「こくが足りない」と述べてはゐるが、それまでの「史記研究」(注釈)に疑問を呈するところもあり、新たな視座を与へてくれる。
「本紀——中国の弁証法——」では、「項羽本紀」「高祖本紀」について述べた後、「四段弁証法」と題して次のやうに語る。
司馬遷は一種の弁証法を用い、歴史は対立と統合とによって新局面が成立すると考えて、黄帝以来、漢の高祖に至るまでを記述して来たが、高祖以後はほぼ安定した時代が続き、少くも武帝時代までは対立、統合の革命が起らなかった。この時代を司馬遷が歴史上に如何に位置付けようとしたかが問題であるが、これを解決するためには、司馬遷を初めとする中国人が、時間的推移を理解しようとする時に用いる思考形式を検討する必要があろう。
中国人は時間的推移を分解して周期とし、その一周期を四分する傾向を有する。先づ自然的な時間では一年を周期としてこれを春夏秋冬の四季に分ける。…最も短い周期は一日であるが、…中国では朝、昼、夕、夜と四区分することが行われる。これが文学上では詩の絶句の上に、起、承、転、結(また合)となって現れる。
ところでこの起、承、転、結の四段階を、現今一般に考えられている弁証法の正、反、合の三段階に比べてみると、一段階多い。どこが多いのかと言えば、起は正に、転は反に、結は合に相い応ずるから、食み出したのは承である。すなわち中国的の思考形式では、正がすぐに反に当面するのでなく、ある期間延長して、承の時間を経過した後に、反に出遇って対立が生じ、最後にそれが統合されて、そこに新しい正が生ずるのである。歴史の発展を説明するための形式としては、正、反、合の三段階よりも起、承、転、結の四段階を以てする方がより適切であるように私には思われる。
また、宮崎は、司馬遷の『史記』執筆の情熱を評価して次のやうに語る。
…同じく歴史を編纂すると言っても、今日我々が情報過多に悩まされ、選択のむつかしさを喞つのに反し、司馬遷の場合は極度の資料不足に困惑したであろう。だから今日の我々が司馬遷に対して感謝すべきは、独創的な史書の体裁、後人の及び難い流暢なる行文などの外に、よくぞこれだけの史料を纏めて保存してくれた、という純然たる史学の基本作業の上の功績である。もちろん欲を言えば限りのないことであるが、もし史記がなければ、どれほど多くの史実が泯滅してしまったであろうか。史記を評価するには何よりもこの観点を忘れてはならぬと思う。
ただし、宮崎は、司馬遷の記述を鵜呑みにはしない。「田敬仲完世家」について語った後で、「古代封建制の崩壊」の段で、「古代のいわゆる封建制度は、徐々に変質、崩壊しつつあり、これに代わる郡県制度もまた徐々に姿を現し、徐々に生長しつつあったのである。そしていわゆる古代の封建制度なるものも、果たして中国の学者が信じていたような、秩序の原理として実在したか否かも、今日から見て一概に信用はできかねるのである。」と述べる。そして、司馬遷の素朴さを苦笑する。
司馬遷は周の武王、成王以下、王権による一族封建の経過をそのまま史実として堅く信じていたようである。併し今日から考えれば、系図は後世から如何ようにも造られ得るものである。…
司馬遷の考えでは、地方政権がその土地、人民を支配するには、必ず中央の天子の委任を受ける必要があると信じた。これは儒家の春秋の学説である。そこで司馬遷は更に、それが歴史上にも実際に遵守されたと信じた。そこで春秋戦国間の割拠政権は、必ず何れかの時代に一たび周の天子から封建の命を受けたと信じ、それを世家の中に書きこんだ。併し私には呉、越、楚など明らかに異民族出自の国君がそのような手続きを踏んだとは考えられない。秦や燕もまた同じ。春秋も末になって、新興の趙、魏、韓、さては田氏斉にも天子の封建の命を受けようなどという健気な志がありそうには思われない。何でも書いてあることならば直ぐに信じこむ司馬遷の態度を笑う私は、当然の帰結として、司馬遷が書いたことを、何でもそのまま呑み込む気にはなれないのである。
司馬遷は、史料の無いことは書かなかつたとされるが、冷静に考へればあり得ない話や出来過ぎた話も少なくない。司馬遷の拠つた史料(史書や古老の話)自体が、書き継がれる(語り継がれる)うちに誇張や創作(物語化)を生むのは自然の成り行きだらう。
最後に、宮崎は、司馬遷が『史記』を書いた動機について、父・司馬談の遺言を、俯首流涕して聞き、その言葉に遵ふことを誓つて、父の職・太史令に任ぜられると、史記の著述に専念したと言ふ。さらに「太史公自序」について語り、次の言葉でこの著を結ぶ。
宮刑を受けた後の司馬遷は、宦者として武帝の宮中に仕へた。彼はその文才を以て武帝に信任され、中書令に任ぜられたというが、併しその境遇は以前のような光輝に満ちたものではなかった。若しも彼の存在が目立つならば目立つほど、その背後の陰翳も亦たいよいよ暗黒さを増すばかりであった。そのような中にあって、現在に失望した司馬遷はひたすら修史の事業に精魂を傾けるより外に安心を得る途がなかった。最早や彼の関心事は、過去と未来しかなかった。自分の著作は何時の日か将来において、世人の目にとまり、世人の心の中に司馬遷が再生するであろうという希望である。司馬遷が恰も目前に起った事象に対するかの如き情熱を以て、過去を語ることができたのは、彼が本来の自由人に立ち返り、現在を忘れて、後世の人に向って語りかけようとしたからに外ならないのだ。

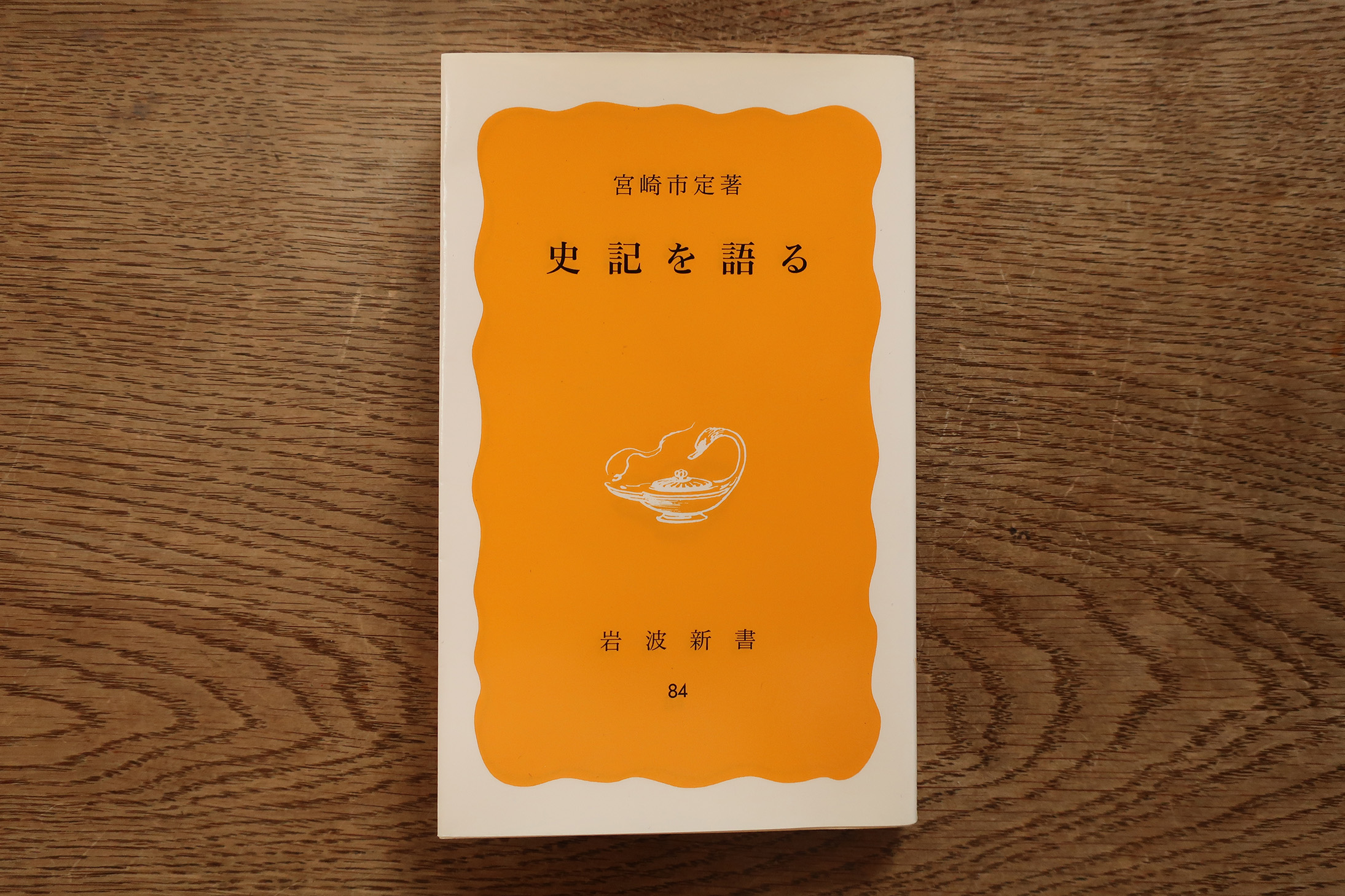


コメント