2025.02.01
山本佳奈『貧血大国・日本 放置されてきた国民病の原因と対策』(光文社新書)読了。
数年前に購入したまま積ん読になつてゐた新書である。なぜこの本を読まうと思つたかといふと、小生自身が貧血だからである。職場の健康診断では、毎年必ず血液検査の貧血の項目で要二次検診または要治療になる。医師からは、赤血球数も血色素量(ヘモグロビン値)もヘマトクリット値も男性としては珍しいくらゐ低いと言はれ、偏食を疑はれるのだが、小生、偏食はまつたく無い。牛肉も鮪も食べるし(経済的制約はあるが)、鰤も鰯も蜆も食べるし、卵も菠薐草もプルーンも食べる。ケールの青汁を毎日飲み、朝のオムレツは鉄のフライパンで作つてゐる。若い頃からずつと貧血だつたので、脳梗塞や大腸癌から来るものでもない。血液の精密検査も受けたが、特に理由は判らなかつた。おそらく体質なのだらう。
この本では、特に日本の若い女性を中心に貧血(鉄欠乏症)の問題を解説してゐる。若い女性は、生理(月経)もあり貧血になりやすいし、当然だらう。
この本に拠りながら、日本の貧血の問題について整理しておく。
血液中の鉄のもつとも重要な役割は酸素の運搬である。貧血になると、酸素を体の隅々まで運んだり、貯蔵したりすることが難しくなり、さまざまな組織で酸欠状態が引き起こされる。その結果、頭痛・肩凝り・眩暈・疲れやすいなどさまざまな症状が現れることがある。また、乳児期に鉄欠乏性貧血の子どもは、IQ・認知機能・視覚運動統合・言語能力が低い傾向があるといふ。
健康な日本人女性1万3000人以上を対象にした調査では、50歳未満の日本人女性の22.3%が貧血ださうだ。また、妊婦の30〜40%が貧血で、これは先進国の平均18%よりも圧倒的に低く、どちらかといへば発展途上国の56%に近い。貧血の妊婦の子どもは、低体重出生児になるリスクが増えるなど、胎児に悪影響もあるので大きな問題である。
一般には、貧血の最大の原因は食事である。発展途上国や新興国(中国・ブラジルなど)の農村地域で貧血が多いのは、貧困による栄養不良によるものである。肉や魚などヘム鉄(非ヘム鉄よりも吸収しやすい)を含む食品は比較的高価なので、経済的格差がより反映される。
近年経済格差が拡がり相対的貧困の比率が高まつてゐるとはいへ、発展途上国のやうに飢餓に陥る人がさう多くないはずの日本で貧血が多い原因は、ヘム鉄を多く含む肉類の摂取が少ない食生活にある。日本の国民一人あたりの牛豚鶏肉の消費量は、アメリカの半分以下である。(アメリカでは、ファストフードや加工食品に依存した食生活が貧血や生活習慣病を引き起こしてゐるが…。)食生活が欧米化してゐるとはいへ、伝統的な食生活が基本にあるので、どうしても肉を食べる機会は欧米よりも少なくなるだらう。(勿論、和食には素晴らしい点も多いが、ここでは貧血に関しての話である。)
また、女性の場合、不適切なダイエットも貧血の理由の一つである。(現代の日本の20代女性の平均エネルギー摂取量は、戦後の食糧難の時代の都市部の人の平均エネルギー摂取量よりも少ないといふ。)山本もこの本の中で、「食事を抜いたり、偏食したり、という間違ったダイエット方法で減量を続けることは、栄養不足に留まらず、骨粗鬆症や生理不順をも引き起こしますし、拒食症などの摂食障害につながってしまうこともあります。」と注意を喚起してゐる。偏つた食生活を奨めるやうなダイエットは無責任極まりないと思ふ。健康的見地からは痩せすぎの、いはゆる「モデル体型」を理想的だと思ひ込んでしまふことは、先進国に共通の社会問題である。摂食障害による痩せすぎモデルの死亡者が続いたことから、イタリア・スペイン・フランスなどの国では、痩せすぎモデルを規制する法律が作られたりもしてゐる。
欧米や一部の途上国では、鉄を添加した食品を推奨するなど鉄欠乏を予防するための政策が取られてゐる。しかし、日本は「ほとんど無策」で何もしてゐない。現状では、各自が問題意識を持ち、鉄分の多い食事を摂つたり、必要に応じてサプリメントも利用したりするなどするしかないが、個人でできることには限界がある。特に、貧困家庭は食生活の改善がなかなか難しい場合もある。各国の貧血対策に、日本も学ぶべき点があるのではないか。
この本では、若い女性を中心に書かれてゐると言つたが、勿論、男性や高齢者の場合にも触れてゐる。高齢者の場合、貧血に他の病気が関係してゐることが多い。定期的に血液検査を含む健康診断を受け、病気の早期発見や予防に努めることが大事だらう。健康寿命が延びることは、社会保障費の削減や労働不足の解消にも繋がる。
山本が最後に述べてゐるやうに、小生も「日本が『貧血対策の先進国』となること」を願つてゐる。

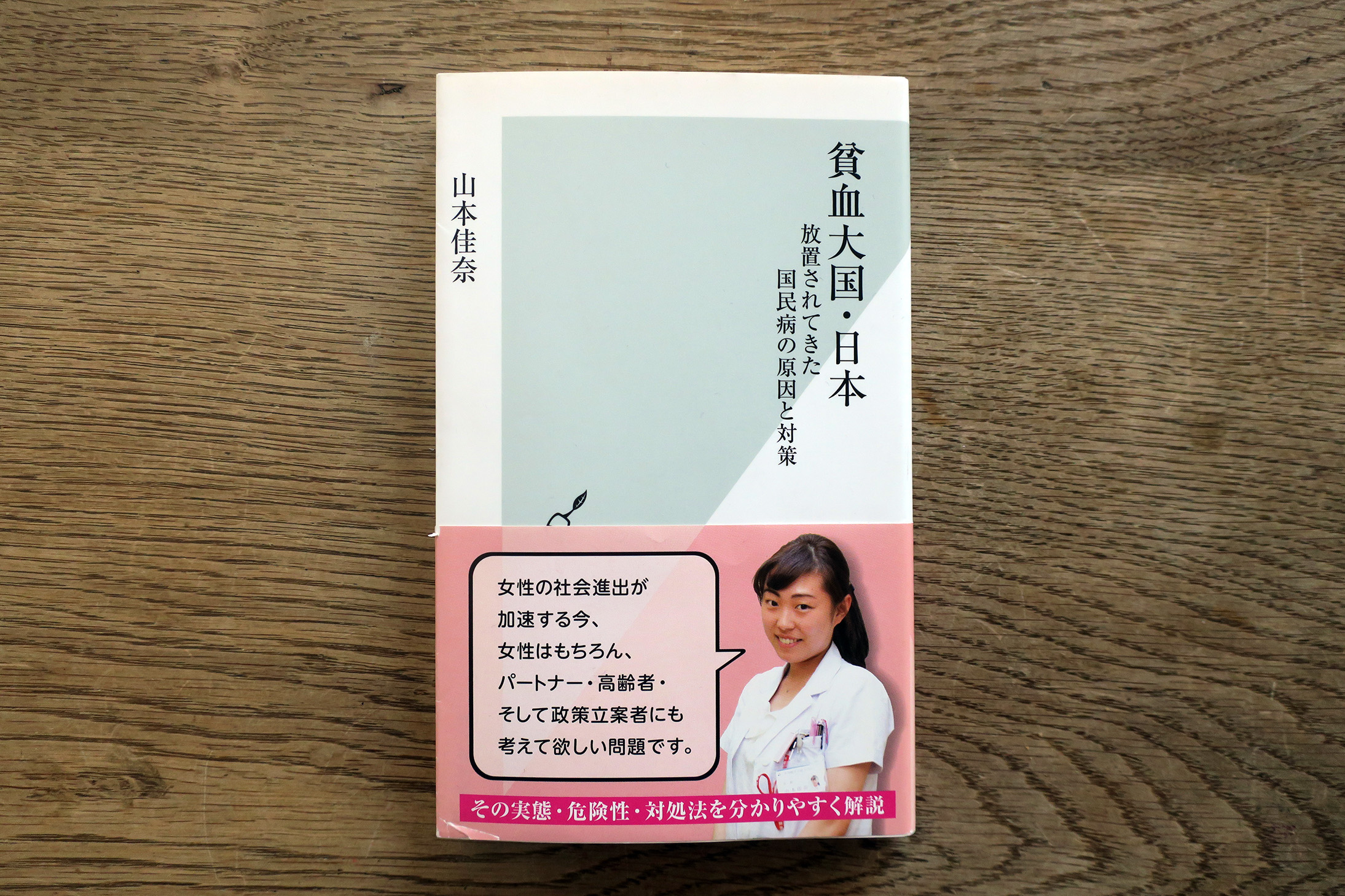


コメント