2025.02.24
鈴木大裕『崩壊する日本の公教育』(講談社+α新書)読了。
著者の鈴木は、アメリカのスタンフォード大学教育学大学院修了後、千葉市の公立中学校の英語教員を務め、再度渡米しコロンビア大学教育大学院博士課程で学ぶ。現在は、高知県在住。他に『崩壊するアメリカの公教育 日本への警鐘』(講談社+α新書)の著がある。
鈴木と小生とで認識や意見の異なる部分もあるが、日本の公教育が危機に瀕してゐるといふ鈴木の主張には共感するところが多い。例へば、次のやうな認識は、多くの教員に共通するところだらう。
今、「教員はサービス業」という認識が、教員の間でも普通になりつつある。それを支えている新自由主義的な世界観は、フランスの哲学者、ミシェル・フーコーの解釈を借りれば、社会のあらゆる活動や関係を経済的な価値観のみで分析しようとする偏った世界観だ。それは、教育までをも「付加価値的な投資」と見なし、生徒・保護者を学費や納税で教育という「商品」を購入する「お客様」、教員を教育という「サービス」を提供するサービス労働者、教育委員会はクレームを受けつけるカスタマーサービスへと置き換えてしまう。「教育委員会に訴えてやる!」そんな言葉を聞いたことのある人も少なくないだろう。教員が子どもの機嫌をとろうとするのも、生徒に対する強い指導が難しくなってきているのも当然だ。
日本の教員の労働時間は、先進国最長である。OECD(経済協力開発機構)の国際教員調査「 TALIS2018」によれば、日本の中学校教員(フルタイム勤務者)の勤務時間を見ると、全体の56.7%が週60時間以上働いている。イギリス28.9%、アメリカ22.0%、韓国7.8%、スウェーデン2.9%、フランス2.6%に比べて著しく高い。平均値にすると週59.3時間で、こちらも先進国では最も高い。その原因は、日本の教員の受け持つ業務が多過ぎることだ。その最大のものは「部活動指導」と「書類作り」だが、他にも「登下校時間の指導・見守り」「学校徴収金の徴収事務」「学校広報」「地域のボランティアとの連絡調整」など他国では教員が担ふことがほとんどないものまでも教員が請け負はされてゐる。そのため、長い労働時間の中で一番大事な教員の仕事である授業の準備や教材研究に割く時間は他国と比較して少ない。しかも給特法で4%の教職調整額(時間にして19分弱に相当)が付く代はりに残業代は出ない。(10%になつたとしても47分相当程度で、実際の超過勤務には遥かに及ばない。)さらにモンスター・ペアレンツへの対応などで疲弊してゐる実態を知れば、若者が教職を志望しなくなるのも当然だらう。かうした状況から教員不足は深刻で、産休や病休の補充も困難で欠員のまま他の教員が授業を補ひ、通常あり得ないほどの過労働になつてゐることも多い。4月当初から担任不在の学校も少なくない。高校生の団体が、学校教育の質の低下を憂ひ、改善を求める陳情を文部科学省に提出する事態にまでなつてゐる。
安倍政権は、地域・学校間の過度な競争を招いたことなどを理由に1964年に中止された「全国学力テスト」を悉皆式で再開し、その結果を従来の自治体別だけでなく学校別に開示できるように規制緩和した。(実は、一般的な社会科学の見解では、調査対象となるすべての人を調査する必要は無い。むしろ抽出式で必要最小限の対象を調査する方が、適切に実態を把握できる可能性が高まる。)そして、吉村洋文大阪市長(現大阪府知事)は、全国学力テストの結果を、校長や教員の人事評価やボーナス、そして学校予算に反映させるといふ、いはゆる「メリットペイ制度」(能力給制度)の導入を打ち出したが、そのことに対する鈴木の批判も引用しておく。
アメリカの教育現場にメリットペイ制度が導入され始めたのは1980年代であり、今から半世紀近くも前のことだ。その後、弊害が次々に露呈し、新自由主義教育「改革」の中では化石のように古びた印象さえある。だから大阪市の多くの教育関係者たちは、そのような制度を市はなぜ今になって導入しようとしたのか、と首をかしげていた。
教育関係者が疑問に思うのも無理はない。そこには教育学の知見に基づいた深い理由などないのだから。端的に言えば、教育の素人である新自由主義者の政治家らが、専門外である教育への介入を強め、公教育も市場化と民営化によって「改革」できるという単純で間違った答えにたどり着いただけのことだ。
新自由主義社会では、政府は電気、保険、鉄道、郵政など、公共として行っていた事業を民営化し、「市場」に委ねる。政府はその市場を管理し、まだ民営化されていない領域には新たな市場を作り出す役割を担う。だから水道に続き、公教育という新たな市場を開拓しようとしたのも、新自由主義の教科書通りのシナリオなのだ。
ちなみに大阪府では府が独自に取り入れた「チャレンジテスト」という学力テストを行っているが、そのテストでは生徒個人だけでなく個々の中学校の偏差値までもが算出され、生徒たちが高校を受験する際の内申点に影響を及ぼす仕組みになっている。…
2016年に広島で行われた教育シンポジウムでは、大阪の教員が紹介したエピソードが会場をどよめかせた。チャレンジテスト前日、成績の悪い生徒が、「明日は学校を休もうかな」と言ったら、それを聞いた周りの生徒たちから拍手が起きたというのだ。なんというグロテスクな環境に子どもたちは閉じ込められているのだろうか。
これは、明らかに行政がいじめを誘発してゐるのではないか。また、他県でも、学力テストの結果が公表されることが圧力となり、テストの前は本来の授業を潰してテスト対策に明け暮れるといふ本末転倒の事態が蔓延してゐる。テストの結果を気にした生徒や教員の不正も起こつてゐる。
また、小泉政権の新自由主義的政策により、国立大学が法人化された。運営費交付金は徐々に減額され、授業料値上げなど学生の負担は増えた。学術研究費も減らされ、国立大学の研究環境は衰退してゐる。また、安倍政権の「選択と集中」政策により、短期的な成果を追求する傾向が強まり、基礎研究がおろそかになるといふ深刻な問題も指摘されてゐる。
国から教育機関への支出の対GDP比は、各国の予算において教育がどの程度重要視されてゐるかを測る重要な尺度である。すべてのOECD加盟国がGDPのかなりの割合を教育機関にあててゐる中、2019年の高等教育機関に対する支出の対GDP比は、日本は4.0%とかなり低い(OECD平均は4.9%)。さらに昨今の円安や物価高による経費の増加によつて、国立大学では、教員や若手研究者の確保など質の高い教育研究の維持が難しくなりつつある。研究者の海外への流出も深刻な問題である。それどころか多くの国立大学で施設の修繕をする予算も無い状況になつてゐる。
また、少子化に伴ひ、文部科学省や教育委員会は、公立学校を統廃合し、教員の採用を控へて教育予算を減らしたが、それも愚かな政策であつた。教育予算を増額しなくても現状を維持するだけで、少子化の進行に伴つて自然と少人数学級が実現できたはずである。日本の高校の学級定数は40人だが、ヨーロッパではおほむね20人以下である。20人学級・25人学級といつた少人数学級が実現すれば、教員の多忙も緩和されたはずである。生徒一人一人に目も行き届き、生徒の個性や能力を生かすこともしやすくなつたはずなのに…。しかも、ある時期の教員の採用を大幅に減らしたせゐで、教員の年齢構成が極端にいびつになるといふ弊害も生んだ。
国土が狭く資源の限られた日本が持続的に経済成長をするには、文化や科学技術の発展が必須であり、質の高い教育を広く普及させることで労働の質を高めることも必要だと思ふのだが…。目の前の利益しか見えない政治家や官僚の辞書には、「教育は国家百年の計」といふ言葉は存在しないのだらう。
また、国立大学の法人化に伴ひ、国立大学は政府に事業計画を提出する義務が発生し、以前よりも国立大学に対する政府の支配は強まつてゐる。 菅政権の時の「日本学術会議会員」の任命拒否も記憶に新しい。政府に批判的な学者を排除しようとしたものだ。その時は、インターネットなどでは公的な組織は国の方針に従ふのが当然だといふ意見も少なくなかつたが(ただし自民党は以前から業者を使つてインターネットの意見を操作してゐたことが発覚した)、政府を批判することがタブーになれば、安倍派の裏金作りなど与党政治家の不正を告発することもしづらくなるだらう。その先にあるのは、ロシアや中国や北朝鮮のやうな独裁国家である。
安倍・菅政権に顕著な傾向の一つが、専門知の軽視である。第一次安倍政権の際に発足した「教育再生会議」の初期メンバーに、大学教員はゐても教育学の専門家がゐないことは当時も批判されてゐた。現場の教員の代表はヤンキー先生こと義家弘介だけであり(隂山英男が小学校の副校長だつたが)、ワタミ社長の渡邉美樹などが名を連ねてゐた。(「和民」で起きた過労自殺の遺族が、ワタミや創業者を訴えていた「ワタミ過労自殺裁判」は、2015年12月に東京地裁で和解が成立したが、和解金は1億3000万円超にも及んだ。かうしたブラック企業の社長が「教育再生会議」の委員にふさはしいと思ふ人は少ないだらう。)その「教育再生会議」の提言によつて「教員免許更新制」が2009年4月から導入された。これが、現在の教員不足の一因にもなつてゐる。その後「教員免許更新制」のさまざまな弊害が明らかになり、2022年に廃止された。しかし、「教員免許更新制」を導入した際には、教員には教育に関する最新の知識や高度な技術が必要としたにも関はらず(患者の命を預かる医師免許は更新不要なのはなぜだらう)、昨今の教員不足から、教員免許を持たない外部専門人材を採用したり、教員採用試験で(合格後の取得を条件にしてはゐるが)教員免許を持たない社会人や大学3年生らに門戸を開く自治体が相次いだりなど、誰がどう考へても矛盾してゐる。
その後、安倍元首相が「愛国心」を唱へながら、教典「原理講論」の韓国版に「日本はサタン(悪魔)の国」であると記されてゐる「統一教会」(一部の国ではカルト認定されてゐる)と密接な関係を持つてゐたことが明らかになつた。やはり一時の政権の意向で学問や教育が支配されるのは、怖い。一時の多数意見や権力者の意向が客観的事実や学問的真実と一致しないのは、ガリレオが地動説を主張して投獄されたことからも明らかだらう。学問や教育は、政府(権力)から自由であるべきだといふのは、ヨーロッパでは一般的な考へ方である。
子どもたちのために豊かな教育環境を整へることは、現在の大人の責任であり、それが将来の日本の発展の礎になる。
教員定数の問題など、現場の教員の努力ではどうもならない部分もあるが(教職員組合や教育学者は教員を増やし少人数学級を実現するやう主張したりもしてゐるが)、教員一人一人の意識も重要である。最後に鈴木の文章を引用して、ささやかな希望としたい。
人々が商品交換モードに支配され、人間らしいモノ・カネの世の中でも、他者への共感を忘れず、公平を求め、お互いが「こぼれ落ちないように支え合う」人間関係の残る「すきま」を楽しめる、またはそういう空間を自らつくり出せる子どもを育てること。そうした子どもたちが増えることで、社会は失われていたバランスを少しずつ取り戻していく。いち教員である「わたし」にできることは、決して少なくない。

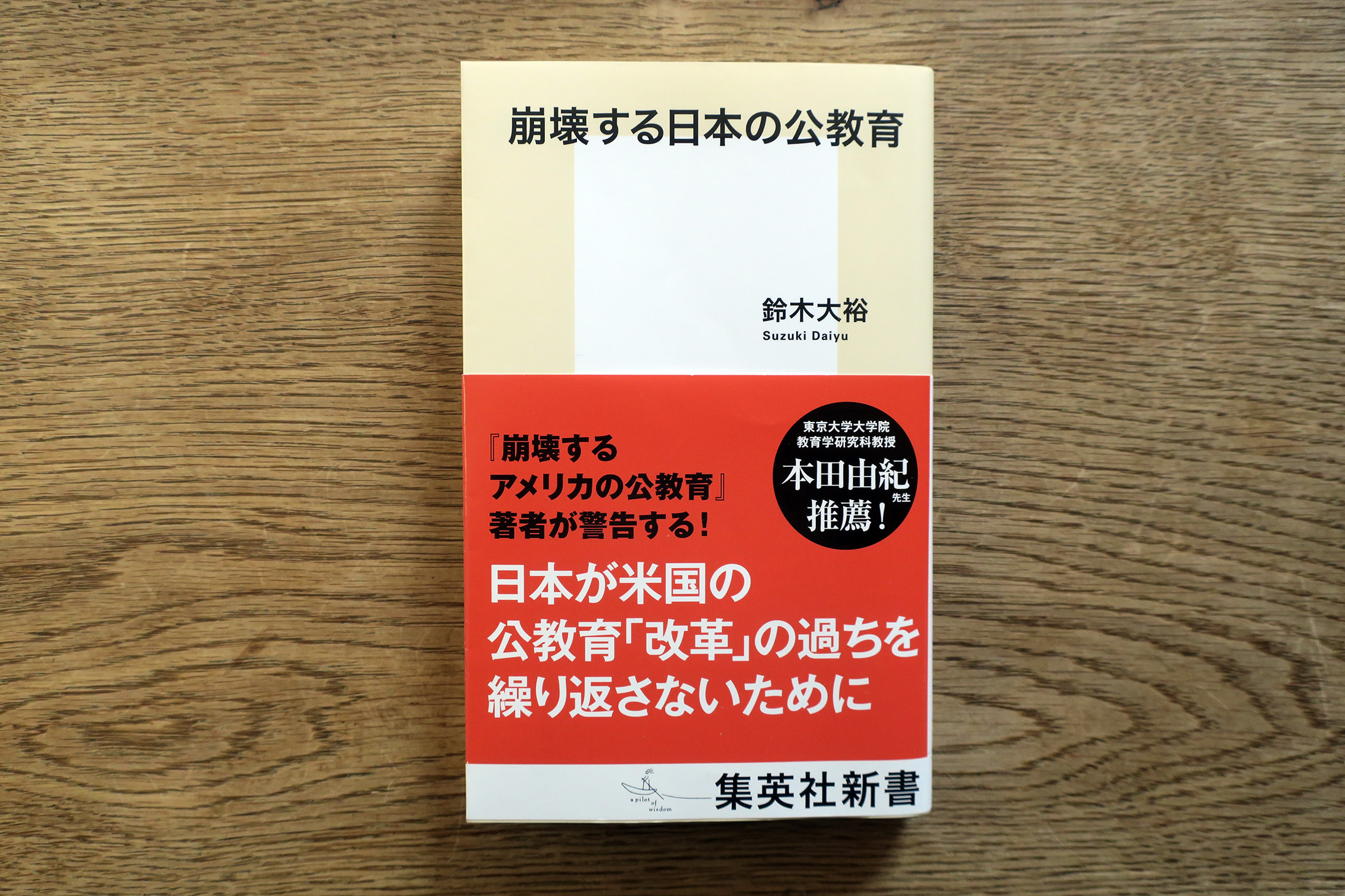


コメント